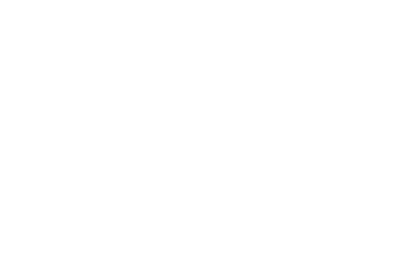
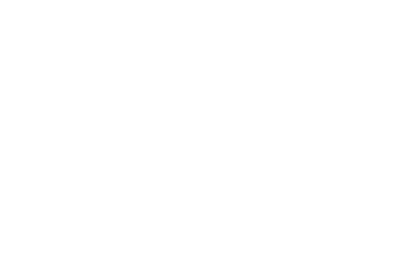
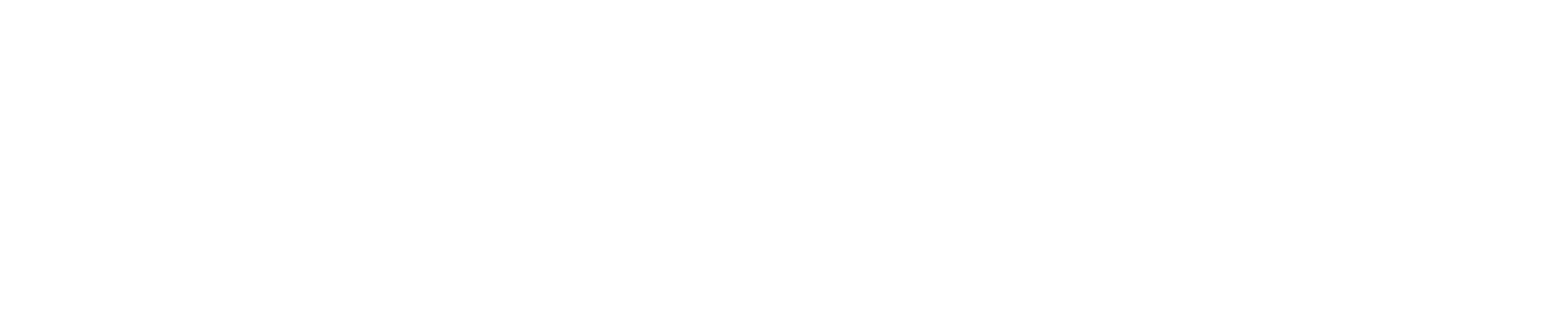
租税公課とは何かご存知でしょうか。
確定申告などの際に、勘定科目として見るものという印象もあるかと思います。
この経費で落とすことのできる租税公課についてご説明します。
租税公課は、租税と公課を合わせた費用勘定科目です。
租税は国税や地方税などの税金で、公課は国や地方公共団体などへの会費や公的課金などのことを言います。
租税公課は損益計算書の費用勘定科目に当てはまるため、経費で落とすことができます。
対象となる租税公課については、また後ほどご説明いたします。
租税公課と似たもので、諸税公課という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
租税公課と諸税公課を分けているところもあるかもしれませんが、勘定科目としては同じものです。
違いは特にありませんので、処理する際にはご確認ください。
意外かもしれませんが、収入印紙や消費税なども租税公課として計上できます。
それでは、租税公課の対象となる主なものを具体的にご紹介します。
具体的には、以下が主な租税です。
*不動産取得税
*固定資産税
*都市計画税
*登録免許税
*印紙税
*事業税・個人事業税
*事業所税
*償却資産税
*消費税(簡易課税制度も要確認)
*自動車税
ただし、事業に使用しなかったり関連しなかったりする税金については、経費として認められません。
自宅を事業所として使用している場合や、自動車を公私分けずに使用している場合は、事業分を按分して計算します。
公課となるのは、以下のように支払ったものです。
*住民票や印鑑証明書などの発行手数料
*公共サービスにかかる手数料
*地方公共団体や組合などの会費・組合費など
公共サービスなどに支払ったら、公課になると覚えておいても良いかもしれません。
個人にかかる税は基本的に租税公課となりません。
以下は、主に租税公課の対象とならないものです。
*個人にかかる税金(所得税や住民税)
*相続税
*贈与税
*法人税
*加算税や延滞税(国税)、延滞金や加算金(地方税)
*罰金など罰則的なもの
租税公課における消費税は原則的に不課税です。
ただし、金券ショップなどで収入印紙を購入する場合に消費税は課税され、消費税も租税公課の対象となります。
租税公課の計算方法については、対象となる租税に記した各種税からご確認ください。
損金算入できる租税公課は、確定申告の際に経費とできるかできないかで大方判断できます。
個人にかかる税金や法人税などは損金算入できませんが、法人税額から控除されない所得税や外国法人は損金算入が可能です。
また、原則的に延滞金は損金算入できませんが、納期限の延長による延滞金は損金算入できますので、確定申告の際には確認することをおすすめいたします。
個人事業主などで青色申告をしている方は、経費にできず損金算入できない税金についてどうすればいいか疑問に思われるかと思います。
固定資産税や自動車税など按分した分や、租税公課として経費にできない税金を納めた場合には、勘定科目は事業主貸で処理しましょう。
経費にできなくても、税額を計算する際に控除対象とできるものもありますので、確定申告の際にはご相談いただければと思います。
租税公課とは、税金を経費とするための勘定科目です。
経費とできる税金とできない税金が租税公課にはありますので、確定申告の際には注意しておきましょう。
時期的にも確定申告が迫っていますので、期限までに手続きできるようご注意ください。
☎:無料相談ダイヤル 0120-485-485
✉:無料面談のお問い合わせはコチラ